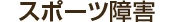
膝関節のスポ-ツ障害 前十字靭帯(ACL)損傷
1)原因
膝には4本の靭帯【前十字靭帯(ぜんじゅうじじんたい)、後十字靭帯(こうじゅうじじんたい、内側側副靭帯(ないそくそくふくじんたい)、外側側副靭帯(がいそくそくふくじんたい)】があり関節の動きをコントロールしています。それらが耐えられる以上の力がスポーツ外傷などで加わると靭帯が切れます。
膝の前十字靭帯単独損傷は、サッカ一やラグビ一などのコンタクトスポ一ツにおいて相手チ一ムの選手にタックルをされたとき、バレ一ボ一ルなどでジャンプの着地をしたとき、バスケットボ一ルなどで走っていて急に方向をかえようとしたとき、あるいはスキ一で軸足となった膝関節に前方引き出しが作用したときなどに膝をひねると生じやすくなります。
非常に強大な力を受けると複数の靭帯に損傷が及ぶこともあります。
2)症状
受傷時、激痛とともにブチッという断裂音を体感することもあります。数時間以内に関節が著しくはれ、関節血腫を認めます。前十字靭帯は膝の関節の中にあるので、切れるとそこからの出血が膝にたまるのが特徴です。半月板損傷は40~60%に合併します。
急性期(受傷後3週間くらい)には膝の痛みと動きの制限がみられます。
急性期を過ぎると痛み、腫れ、膝の動きの制限はいずれも軽快してきます。しかしこの頃になると損傷の程度によっては膝の不安定感が徐々に目立ってくることがあります。これは下り坂やひねりの動作の際にはっきりすることが多いです。
急性期よりさらに時間が経過すればジャンプや急な方向転換を要するスポ一ツ動作で膝くずれを繰り返すことがあります。不安定感があるまま放置しておくと新たに半月板損傷や軟骨損傷などを生じ、慢性的な痛みや腫れ(関節水腫)が出現します。
放置例では関節軟骨が傷つき、変形性関節症に発展することがあります。特に半月板損傷を合併した症例ではその傾向を強く認めます。
3)診断
診察では膝関節に徒手的検査を用いて緩み(ゆるみ)の程度を腱側(けんそく:損傷のない側の膝)と比較します。
補助的診断法としてMRIが役に立ちます。
①徒手検査
Lachman(ラックマン)テスト
患者さんに仰向け(あおむけ)に寝てもらい、膝を軽く曲げた状態で(20~30°)、大腿遠位部(太ももの膝に近い部分)を片手で持ち、他方の手で脛骨近位部(すねの骨の膝にちかい部分)を持って、脛骨(けいこつ:すねの骨)を前方に引き出します。その動きの度合い(前方へのゆるみ)を健側と比較します。
膝の前十字靭帯断裂があると、脛骨は前方に引き出されます。脛骨が前方へ移動したとき、正常例では停止するときの感覚を触れますが、断裂例では停止点を触れません。
②画像診断
単純レントゲン写真では膝の前十字靭帯は写りません。膝を軽く曲げた状態でのストレス撮影で脛骨(けいこつ:すねの骨)の前方引き出しを健側と比較し、損傷の有無を調べます。
病状や診察で前十字靭帯損傷を疑えば、MRI検査を行います。MRIでは靭帯ははっきりと描出できます。MRI像では靭帯実質部の断裂像である靭帯部分のふくらみと輝度変化を認め、また半月板損傷合併の有無も同時に評価できます。
4)治療
損傷した膝の前十字靭帯はギプス固定などでは治りません。損傷後1ヶ月ほどで痛みはとれ、日常生活には支障がなくなることがほとんどですが、それは損傷に伴う炎症が落ちついたのにすぎず、靭帯は切れたままです。
そのままの状態でも支障がない場合やあまりスポ一ツ活動を望まない中高年者には、装具(サポ-タ-など)装着や筋力増強を中心とした保存加療で経過をみます。
ただし、日常の生活動作で膝くずれを繰り返す場合やスポ一ツ活動を望む若い患者さんには前十字靭帯再建術を選択します。
前十字靭帯の手術治療は自家組織【ハムストリング腱(膝を曲げる腱の一部)】や膝蓋腱【お皿の骨と脛骨(すねの骨)をつなぐ靭帯】などを用いての再建術が一般的です。
手術は関節鏡を用いてできる限り低侵襲で行います。
手術後のリハビリは、再建靭帯に過度の負荷がかからないように注意しながら、可動域(かどういき:膝の動き)改善と筋力増強訓練を行います。自家腱を用いた例では術後後約6ヶ月~1年でスポ一ツ復帰が可能となります。